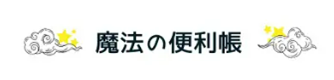4~5月の旬の「たけのこ」。おもいがけなくご近所さんからいただいて喜んだものの「あれ、たけのこってどう処理するの?」なんて後から気付いて困った経験はありませんか?
「ぬか」のあく抜きレシピはよく見かけるけれど、ひと手間かけて今日はワンランク上の香ばしい「たけのこ」のあく抜きレシピに挑戦してみてください。
炒った「米ぬか」を使えば、香りと風味豊かな絶品タケノコに仕上がります。

教えてくれたのは、毎年たけのこ狩りでお世話になっている
「たけのこの里」富沢町の農家のお婆ちゃんです。
毎年、お庭の「かまど」でコトコトと煮てくれます。

「炒りぬか」を使ったタケノコあく抜き方法
日にちが経ってしまった「たけのこ」ほどアクが強いです。
早めにあく取りをして保存する事をお勧めします。筍の保存方法もレシピ下部に紹介しているので参考にしてください。
「炒りぬか」を使ったタケノコあく抜き方法 材料

| 材料 1鍋分 | 分量 |
|---|---|
| 鍋 | タケノコが入る大きな鍋 |
| 筍 | 3~4本 |
| 米ぬか | ひとにぎり |
| 鷹の爪(赤い唐辛子) | 1本 |
| 水 | タケノコがかぶる量 |
1.筍の下処理

たけのこは新鮮なうちはアクが少ないです。手に入れたらすぐに茹でましょう。剥ける堅い皮はある程度剥いておきます。皮が残っていても大丈夫です。
2.穂先は切り落とす

上部(穂先)は斜めに切り捨てます。

写真のように、成長してしまったものは、硬い茶色くなっていますので使いません。捨てましょう。
3.イボイボの処理

根元にイボイボが付いている場合は、えぐみの原因になるので削ぎ取りましょう。
4.切り込みを入れる

タケノコを縦に切り込みを入れます。
縦に切り込みを入れると火が早く通りやすくなり、茹でた後に簡単に皮がむけます。一カ所だけ、半分の位置に深く切り込みを入れましょう。
堅いので手を切らないように気を付けましょう。
5.炒りぬかを作る
「米ぬか」を鍋に入れる前にひと手間かけて、「炒りぬか」を作りましょう。香ばしい炒りぬかを使ってあく抜きすることでワンランク上の美味しいタケノコに仕上がります。
フライパンで弱火で「ぬか」を5分ほ炒ります。ひとにぎりの「ぬか」をフライパンに入れたら、しゃもじでかき混ぜながら中火にかけます。ぬか全体があたたまってきたら弱火にして3分ほど混ぜて炒れば出来上がりです。
この手間をするかしないかで、格段の味の違いが出ます。最近では、炒った「米ぬか」も売っていますが、自分で炒った物の方が香ばしいのでひと手間かけて作ってくださいね。
6.大きな鍋を用意しよう
たけのこがすっぽり入る大きさの鍋を用意します。
たけのこの穂先を切り落として、残りがすっぽり入るサイズが良いです。
7.落とし蓋を使ってコトコトじっくり茹でる

吹きこぼれないよう注意しながら、弱火で1時間~2時間茹でます(小さな「たけのこ」の場合は40分から1時間)
沸騰してきたらにこぼれないよう気を付けましょう。

「ぬか」もいっしょに吹きこぼれるので後始末が大変です。沸騰してくると、たけのこが浮いてしまって茹でむらが出て変色してしまいます。まんべんなく茹で上がるように落し蓋をしましょう。
太い部分に竹串を刺してみて、スッと通れば火を止めて大丈夫です。鍋に入れたまま、冷めるまで置いておきましょう。すぐに出してしまうとえぐみが残ります。
8.水で洗って皮むき

冷めたら水でよく洗い皮をむき、冷蔵庫で保存。使う時にひと口大に切って使います。
筍ご飯、メンマ煮、チンジャオロースー、中華丼の具など筍は様々な料理に使えるので重宝しますね。
ゆでたタケノコの保存方法
タッパーでの冷蔵保存
タケノコが冷めたら、水で良く洗って切らずに保存します。フタつきのタッパーなど、深めの保存容器にたけのこを入れたら水を入れて完全にひたるようにします。
時間が経つと水が濁るので時々水を変えてあげます。1週間くらいは保存が可能です。
筍の瓶詰で長期保存

長期保存したいなら、瓶保存がおすすめです。タケノコを沢山収穫した年は、瓶保存して翌年のお正月まで保存します。
蓋つきのガラス瓶を用意します。ビンは500mlくらいのもので、100円ショップなどで簡単に手に入ります。
ビンに入るくらいのお湯を沸騰させ、冷ましておきます。
ビンを洗ったら、あく抜き済みのタケノコを縦に切りビンに詰めます。
縦切りにすると、先が細い3角柱のような形になるので、上下交互に詰めるとうまく入ります。
詰めるというか、ビンに縦に挿していく感じです。
詰め終わったら、冷めたお湯をビンぎりぎりまで注ぎ、防腐剤代わりに酢を小さじ一杯いれます。
お湯または水を入れた「大きな鍋」を用意して、ビンを立てて入れます。
鍋の水量はビンの8分目ほどで大丈夫です。ビンの蓋を1度閉めたら、再びゆるめて40分煮ます。
40分後、火傷しないようビンを取り出したら、ビンの蓋を強く締めます。さらに15分煮たら出来上がり。ビンを取り出して、蓋が凹んでいれば成功です。
たけのこ「えぐみ」の仕組みと、相乗効果

たけのこの「えぐみ」は、たけのこに含まれる「シュウ酸」や「ホモゲンチジン酸」が原因だそうです。つまり、この「酸」の部分を中和させてあげると美味しくいただけると言うわけです。
その「えぐみ」を取るのが「米ぬか」でです。
米ぬかに含まれるカルシウムがえぐみ成分を吸着してくれます。加えて、米ぬかに含まれるアミノ酸と脂肪が「たけのこの繊維」も柔らかくしてくれるという相乗効果があります。
最近では、「大根おろし」や「重曹」で簡単に「えぐみ」を取る方法もありますが、この相乗効果を考えると昔ながらの「米ぬか」でのあく抜き方法は先人たちが知恵を絞った最善の方法だと感心しますね。
また、赤唐辛子もぬかに加えると「えぐみ」をとる効果があると言われています。

でも、「たけのこの里」のお婆ちゃんによると、新鮮な筍なら「米ぬかなし」でも十分にアクを取ることができるとのこと。
たけのこ「米ぬかなし」の茹で方や、「大根おろし」や「重曹」でのあく抜きレシピは、別記事で紹介しています。
「炒りぬか」を使ったタケノコあく抜き方法/まとめ
「炒りぬか」を使ったタケノコあく抜き方法
・新鮮なうちにあく抜きすること
・タケノコがひたるくらいの大きな鍋を使う事
・イボイボは取り、切り込みをいれる
・炒りぬかを使う事で香ばしさとうまみがUP
・落とし蓋をしてじっくり1時間
・保存は水を入れて1週間